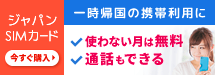Shining mimosa star The 16th Ms. Mariko Watanabe, conservator (Oct issue 2024)
01 Oct 2024

第16回
コンサバター(保存修復師) 渡邉万里子さん(10月号 2024年)
作品が甦る瞬間を、一番近くで感じられる仕事

✿プロフィール 渡邉万里子さん✿
日本で大学卒業後、イギリス南部ウェスト・ディーン・カレッジにて本の保存修復を学ぶ。
卒業後来星。個人経営の保存修復会社での4、5年の勤務を経て2018年より現職。
聞き手・文責・写真
シンガポールミュージアム日本語ガイドグループ
西山ひろ美、森田恵莉華
ー先ず、コンサバターとはどんなお仕事か簡単にご説明いただけますか。
渡邉さん コンサバターは日本語でいうところの保存修復師です。仕事としては大きく二つあります。一つは文化財や芸術作品を、その作品の所属に関わらずそのものが出来るだけいい状態で長く親しんでもらえるように保存状態や展示方法をどのようにすればよいか学芸員の方々にアドバイスしたり、時には一緒に展示方法を考えたりすることです。もう一つは、すでに傷んでしまっているものについて“直す”というと誤解を招くのですが、できるだけ作品が長生きできるような状態にすることです。これは必ずしも新品のようにするということではありません。
ーこの仕事についたきっかけを教えてください。
渡邉さん 日本で西洋古典文学や歴史を勉強していて、授業の一環で西洋の古い本を手にとって見せていただく機会がありました。そういうものに触れるのはその時が初めてでしたが、純粋にいいなぁと思ったんですね。手を動かすことが子供の頃から好きだったというのもあって、古い本に対する興味と、手を動かす仕事という二つをくっつけたような仕事ってないのかなと探してみたところ、本を作るのと傷んでしまった古い本を直すという仕事に行き当たりました。そこからコンサバターを目指すようになりました。
ーコンサバターにはどんな専攻の方が多いのですか?

渡邉さん 私の場合は古典文学でしたが、化学や美術史専攻だった人が割と多いです。いろいろな技術が進んでいくにあたって、保存修復のことを勉強してきた人でも化学がわかっていないと職場で追いつかなくなるというようなことが多くなってきました。
コンサバターが化学的なことを一から十まで自分たちだけで扱わないといけないということは少ないです。けれども実験などを専門の化学者にやってもらってどの修復方法がよいかを一緒に議論するためには、こちらもある程度の知識は必要です。私はイギリスのウェストディーン大学で保存修復について勉強しました。のどかなところにある大学なので他にやることがなくて沢山勉強しましたね(笑)。その紙がどんな性質を持っているか?そういう知識を持っていることで、保存修復の処置の選択肢を並べ、選ぶことができるんです。
ーイギリスの大学で保存修復の勉強をされたんですね、修復というと工房に弟子入りするイメージでした。
渡邉さん 上の世代の方はそっちの方が主流だったかもしれませんね。どっちがいいというのは見方によるのですが、今は大学教育を受けて来てくださいというのが多いです。理論的なことを分かっていないとという人もいれば、手作業の技術が失われてしまうといった意見もあります。どちらも正しいと思います。
ー現在お仕事をなさっているシンガポールのコンサベーションセンターはどんなところですか?
渡邉さん 正式名称はヘリテージコンサベーションセンターといいます。ナショナルヘリテージボードの傘下にある機関で、シンガポールが管理している芸術作品の保管庫の役割を果たしています。6階建のうち半分以上が収蔵庫、残りのエリアがオフィスと保存修復のためのラボになっています。保存修復のチームは全部で30〜40人くらいですが、他にも保存修復化学の専門家やカメラマン、作品の管理をするコレクションマネージャー、データベース管理の担当者もおり、そちらも大体30〜40人くらい。保存修復と収蔵庫の施設としては割と大きな組織だと思います。
ーとても大きな建物ですよね。ガイドツアーにお邪魔させていただいた時にとても驚きました。セキュリティや管理体制も厳重ですよね。
渡邉さん はい。収蔵庫の役割もあるため、建物全体の湿度と温度を常にモニターしていて、何かあったらすぐに対処できるようにしていますね。人の流れも常にチェックされています。シンガポールは温度と湿度がとても高く、外の気温から大体10度低く、湿度は10〜20%低く保つのが理想です。これはこの気候ならではの問題ですね。カビやシミが出来やすくなったり、冷房のオンオフにより温湿度が上下し有機物が拡張と収縮を繰り返してしまい素材が弱ったりという問題があります。日本や欧米は四季があるので、変化する外気に対してどのように対処するか、というまた別の問題がありますね。どのように温湿度を一定に保つかは作品を保存する上で非常に重要ですね。
ーこれまでのお仕事で印象に残っているのはどんな事ですか?
渡邉さん ナショナルギャラリーに展示予定のチェン・ウェン・シー※1の作品が印象深いです。ギボンズという5m×3mのとても大きな作品なのですが、最初に届いたときの状態がとても悪く修復を一年くらいかけて行いました。プロジェクト自体は7年程前から立ち上がっていましたが、新型コロナウイルス(COVID-19)の影響でかなり遅れていました。外部の表具師※2さんと協力してやっと皆さんに見ていただける状態になりました。作品が作家さんの目指した生き生きとした姿になって行くのを一番間近に見ることができる、そういうところにやりがいを感じますね。
ーコンサベーションセンターでのお仕事はどのようなものですか?
年間スケジュールと1日のお仕事を教えてください。
渡邉さん 年間のスケジュールは、その年に開催される各美術館の展示スケジュールに沿って決まります。今はナショナルヘリテージボード傘下の博物館・美術館が10館以上あって、一年で大体10から15くらいのプロジェクトが重なりながら進みます。その内には国外に貸し出す作品の修復もあります。
一日の仕事は修復のほかに、プロジェクト進行管理や展示会のための書類仕事などがあります。あとはアウトリーチの仕事ですね。コンサベーションセンターでガイドツアーを催したり、小学校や中学校へ行って私たちの仕事について話したりしています。私たちの仕事というのはやはり裏方の仕事なのですが、こうして皆さんに知って頂く機会というのも非常に重要なんです。
ー紙の修復に和紙を使うとうかがいました。シンガポールでも使われていますか?
渡邉さん はい。日本の和紙は紙の修復だけでなく他の素材の修復にも使われています。保存修復に適した和紙を意欲的に作っていらっしゃる会社もあります。日本に関連するものは他にもあって、修復用の刷毛ですとか小さな鋏等の道具もコンサベーションセンターの保存修復で使われています。
ー今後、保存修復のお仕事にAIは活用されるのでしょうか?
渡邉さん 職場でもどのように使えるか話し合っています。こういう風に使えるんじゃないか?という一例なんですが、毎月の展示品の状態チェックをAIにしてもらうという案が出ました。図書館でも棚をスキャンして抜けている本がないか、並び順は合っているかの確認をAIを使って行っていると聞きます。そうした確認作業をさせることができないかなど継続的に議論していますね。医療など他の分野から技術や道具を借りて応用していることが多い仕事なので、AIもそういったものの一つになっていくんじゃないかなと思っています。
ー作品ごとに最適な補修方法を選択していると仰っていましたが、どのように決定するのでしょうか?
渡邉さん 一つ一つ作品の通ってきた道があるはずなので、それを汲み取りながら保存修復もその文脈に沿ったかたちで行っています。必ずしも新品のように良い状態にすることが正しいわけではないんです。少ない処置でより良い状態を長く保つというのが目指すところで。どのように使われどのように保存されて来たかという歴史的なところがなるべくわかるようにというのがあります。そのため、修復を行う前と後の状態を写真と文章で残しておくのも非常に重要な仕事の一つです。そうした作品の文脈を読むというのはAIではまだ代替できないところかもしれませんね。
ーお休みの日は何をされていますか?
渡邉さん 休日は2匹の飼い猫と遊んだり、お友達とでかけたりしています。長期休暇の時は、近隣の東南アジアの国をまわったり、時間があればヨーロッパの方まで出かけて本を作るワークショップに参加したりしています。実際に手を動かしてどのように作られているかを知ると、修復するときにもその経験が参考になるんです。イタリアの湖畔にある小さな修道院で開かれたワークショップはとても面白かったです。宗教施設の図書館の保存修復をしようというプロジェクトから始まったワークショップで、毎週異なる種類の本を一週間かけて制作するというものでした。とても贅沢な時間でしたね。そういう時間が一番好きですね。

ー日本人会会員のみなさまに一言お願いします。
渡邉さん コンサバターの仕事は裏方なので目にする機会は少ないと思いますが、修復についての展示などがあったらぜひ足を止めて見て頂けたら嬉しいです。そしてぜひ美術館や博物館に沢山足を運んでください。やはり皆さんに見て頂いてこその作品なので。
コンサバターを目指す方は、ぜひ良いものを沢山見てください。水彩画一枚とっても、どんな筆でどんな絵の具を混ぜて描いたのかな?と想像してみてください。じっくりと観察することを楽しんでみてくださいね。
※1…中国広東省生まれのシンガポールのアーティスト。南洋芸術大学で教鞭をとった。
※2…軸ものや額をつくったり、襖や掛軸を仕立てたりする職人
インタビュー後談
今回のインタビューを通じて、普段博物館で目にしている作品がどのように保存修復されているのかを知ることができました。国外へ作品を貸し出すこと、国内の作品を博物館に展示できる状態まで修復すること、こうしたことは多くの人の手があり実現していることなのだと改めて感じました。作品が新品同様になることが目的ではなく、その歴史的な文脈を含めて作品を出来るだけ長生きさせる、という修復の基本理念にはその作品を生んだ文化や宗教への敬意を感じます。そうした文化財の保存のためにこれだけのスタッフが常駐するシンガポールの博物館は、今後ますます東南アジアの文化財保護について大きな役割を果たしていくと思います。読者のみなさまもシンガポールの博物館にぜひお越しください。きっとまだ知らない素敵な作品に出会えるはずです。お忙しい中インタビューを快くお引き受けいただき、また多くの質問にも真摯にお答えくださった渡邉さんにこの場を借りてあらためてお礼を申し上げます。