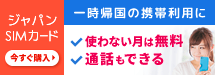Letter from Doctor (Jan Issue) 2025
01 Jan 2025
総合診療科・心療内科 毛利由佳
バイリンガル環境で育てる!?バイリンガルに育てる!?
グローバル化がどんどん進むこの時代。今の子供たちが大きくなるころには、さらにグローバル化が進むでしょう。それに備えて、自分の子どもがバイリンガルやトリリンガルになれたらと考えている方も多いと思います。
特に、人種と言語のるつぼであるシンガポールではバイリンガル、トリリンガルなどマルチリンガルの環境はとても身近です。実際に多くのお子さんがバイリンガルやトリリンガルなどの環境で学習されています。
そういった中で、本当にバイリンガルの環境で育ていって大丈夫なのだろうか?、英語も日本語も中途半端にしか育たないのでは?などと心配される保護者も多くみられます。
バイリンガルの長所、短所、そしてバイリンガルで育てる上で何に着目すべきかをこちらでお話しできたらと思います。
バイリンガルの長所
①認知能力
バイリンガルの人は脳における言語のスイッチを頻回に行うため、脳が複数の情報処理をうまく行えるようになると言われています。マルチタスクの能力が高まったり、問題解決力が上がったり、記憶力や集中力が向上するとも言われています。また、柔軟性や適応性も高まると言われています。
②多角的視点
バイリンガルの人は異なる言語が理解できるため異なる文化を理解しやすくなります。また、言語によって表現や視点が異なるため、様々な角度から物事を思考することができるようになります。多様性も柔軟に受け入れやすくなります。異なる言語を話せることで、将来の選択肢が広がる可能性も高まります。
③思考力・推理力
バイリンガルの人は2つの言語を使いこなすため、論理的に考えたり推理したりする力が強くなると言われています。そのため、相手の言いたいことをより理解しやすくなるとも言われています。
④言語力・コミュニケーション力
バイリンガルの人はモノリンガルと比較して脳の発達構造が異なると言われています。そのため、第3言語の習得がより容易でマルチリンガルとなりやすいと言われています。多言語が話せるため、多文化圏の人々とコミュニケーションが取れ、コミュニケーション能力も高まると言われています。
⑤健康面
バイリンガルの人は認知症の発症が遅れるという研究結果があります。(南十字星2023年10月号の鈴木言語聴覚士のコラムをご参照ください。)さらに、脳卒中からの回復率が高いという報告もあります。異なる言語が理解できることで得られる情報量も変わりますので、幅広く健康の知識を手に入れることも可能です。
バイリンガルの短所
短所はダブルリミテッドです!!
経済的負担や時間的負担、精神的負担を不安に思われる方もいますが、それはバイリンガルそのもののデメリットではないのでここでは省きます。学ぶものが増えれば、これらの負担が増えるのは明確ですよね…言語に限らず。
ダブルリミテッド
いわゆるセミリンガルのこと。どの言語でも発音は良くても、日常生活くらいの話はできても、ちょっと込み入った話になると言葉で表現するのが難しくなります。例えば、英語と日本語のダブルリミテッドの場合、英語と日本語を混ぜたとしても、難しい話ができません。そうなると自分の気持ちを言葉で伝えられないので、情緒不安定になったり、暴力沙汰をおこしやすくなったりします。さらに、社会人になったあとは仕事などビジネスの場でうまくコミュニケーションが取れずに困ったことになる可能性があります。
どうしたら防げるの?
ダブルリミテッドは、どちらの言語も不十分に育ってしまっている状態です。原因としては本人の言語能力も多少は影響しますが、それ以上に環境要因が大きいと考えられています。母語、学習言語のどちらの言語とも十分に触れる時間がなかった時に生じやすいとされます。例えばインターナショナルスクールに通うお子様の中で、学校で英語は触れますがその取り組みが不足していて、さらに家庭での日本語との触れ合いが不十分だとダブルリミテッドが生じやすくなります。なお、幼少期のバイリンガル教育入りたての時期のダブルリミテッド状態は一時的なことが多く、その後の両言語への関わりが良好であれば、バイリンガルに育っていくことが多いと言われています。
母語で年齢相応の学習言語能力を有することが大切!!
言語能力は、生活言語能力(BICS:Basic Interpersonal Communicative Skills)と学習言語能力(CALP:Cognitive Academic Language Proficiency)に区分されます。BICSは日常生活程度のコミュニケーション力、CALPは抽象的概念や概念学習、教科学習に必要な認知・言語能力になります。ダブルリミテッドはどちらの言語もBICSレベルにとどまっています。CALPの力が年齢相応にないと、小学校高学年以上の学習における抽象概念が増えてきたときについていけなくなったり、社会に出て仕事で困ることが起きたりします。
母語は抽象的な概念を理解するのに役立ちます。
両親が日本人の場合、小学校や幼稚園に入る迄は日本語環境で育つお子さんが多いでしょう。
するとそのお子さんの母語は日本語になります。母語とは、その人が生まれてから最初に自然と身につけていった言語のことを言います。幼少時は母語の基盤が弱いので、インターナショナルスクール等に行って、学校で触れる機会が減り、さらに家でも触れなくなるとあっという間に喪失することもあります。しかし、幼稚園からの学習言語がその時点での母語レベルに到達するのには時間がかかるので、抽象的な概念の理解が遅れがちになり、学習言語での認知能力が実年齢より遅れがちになります。この時に母語も育っていないと、学習言語能力が低い状態になってしまいます。そして、そのまま対策も取られずに育ってしまうと、ダブルリミテッドのリスクが高まります。一方で、母語の維持がしっかりとなされていると、母語が抽象概念の理解を助けてくれるため理解しやすくなり、学習言語でも認知能力が年齢相応に保てるため、ダブルリミテッドになるリスクが下がると言われています。特に10歳ころまでは母語以外の新しい言語習得も早いものの、母語の能力を喪失するのも早いと言われています。この10歳ころまでに、しっかりと母語での学習言語能力をつけられているとその後は母語を維持したり伸ばすことは難しくなく、どちらの言語もダブルリミテッドにならずに習得していける可能性が高くなります。
ここまで、バイリンガルの長所と短所を述べてきましたが、これらは海外での研究が元になっていることが多いです。世界的にはバイリンガルなど多言語の研究が多くなされており、多くの研究結果は長所の方が多いという傾向にあります。ただし、これらはヨーロッパ圏内の多言語であったり、ルーツが同じ言語による多言語の研究が多いです。日本語は、ほとんどの言語と文法が大きく異なり、使用している文字も大きく異なります。実は、日本語とのバイリンガルなど多言語の研究はとても少なく、日本語とのバイリンガルやマルチリンガルに関しては分からないことが多いです。たとえば、自閉症スペクトラム障害(ASD)の発達特性があるお子さんは日本語よりも英語の方が理解しやすいというケースもよくみられます。これは行間を読むことを多く強要される日本語と違い、英語は言葉通りにとって問題の起きにくい言語という特徴もあるかもしれません。その結果、母語である日本語よりも英語に頼りがちになる傾向を認めることがあります。また、ASDのお子さんの場合、多言語で学習しているお子さんの方が他人の気持ちの理解度が高いという研究結果もあります。日本語と外国語の多言語習得に関しては、今後の更なる研究が待たれます。
お子さんの言語について、ご不安がある方はお気軽にクリニックにご相談ください。当クリニックは医師と言語聴覚士、公認心理師がチームを組んで、子どもの発達のアセスメントや療育を積極的に行っております。人はみな違います!!個々の子どもたちの得意不得意を知って、明るい未来に繋げていければと考えています!
文責・画像:毛利由佳