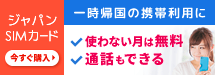Letter from Clinic (July issue) 2023
28 Jun 2023
ソーシャルスキルトレーニング
臨床心理士・公認心理師 坂牧 円春
ソーシャルスキルとは
私たちが社会で他の人と関わりながら生きていくために必要なスキルをソーシャルスキルと表します。人は生まれて成長していく中で、家族や幼稚園・学校の先生、友達、近所の人々などの様々な人と出会いながら、人とどのようにうまく付き合っていくことができるのか、自然に身につけていくことが多いです。
たとえば、どんな時にどのような挨拶をするのか、一緒に遊びたい時にどのように誘えばいいのか、困った時にどのようにヘルプを出せばいいのか、相手に合わせながら会話をするにはどうしたらいいのかなど、親や先生が教えなくても社会生活をしている中で、自然に学べる人もいますが、中には、具体的に教わらないとわかりにくい人もいます。
社会性のつまずきの例
幼児〜低学年
・先生に言われたことができない
・集団遊びについていけない
・感情を表現するのが苦手
・会話がずれてしまう
・大人であれば会話が成り立つが、子ども同士ではうまくいかない
・遊びのルールを理解することが難しい
高学年〜中高生
・その場の雰囲気や状況の判断が難しい
・自分がやられた(被害者)とすぐに勘違いする
・自分の好きなことを一方的に話してしまう
・相手の気持ちがわかりにくい
・自分の気持ちや要求をうまく伝えられない
・1対1の関係であればいいが、3〜4人の関係になるとうまく付き合えない
一つひとつを見ていくと、小さなつまずきであっても、それが長い間、積み重なっていくと、本人の中で不適応の感覚が大きくなってしまうことがあります。
たとえば、先生からの一斉指示に対してすぐに反応できずに周囲と同じタイミングで動けない状況が繰り返されると、周囲からも「いつも遅れる子」と思われたり、本人も「みんながやることについていけない、やりたくない」という思いを感じたりすることもあります。また、友達関係においても、会話がうまく続かなかったり、遊びにうまくついていけなかったりすると、孤立気味になったり、本人からも積極的に関わろうという気持ちが薄れてしまったりすることもあります。
このような集団場面でのうまくいかない経験が、「どうせうまくいかない」「きっと自分だけ怒られるんだ」などという物事をネガティブに捉える考え方を作り上げ、また孤立感、自己肯定感の低下、意欲低下など心理面でのダメージにつながることもあります。
そこで、このようなネガティブ思考のサイクルや心理的ダメージが起こる前に、子どものソーシャルスキルを向上させることが大事です。ソーシャルスキルの向上をめざしたトレーニングがソーシャルスキルトレーニング(SST)です。
ソーシャルスキルトレーニング(SST)の内容
その子の特性、認知能力のバランス・アンバランス、自己調整能力の程度を理解しながら、その子にあったアプローチを考えていきます。内容は一人ひとり異なりますが、以下にあげているのが共通したアプローチです。
・日常生活でよくある場面を呈示する
・どのように行動したらいいか一緒に考える
・実際の場面ではどうしているか話し合う
・お手本をみせる
・ロールプレイをする
・うまくできる体験をする
・ほめる、認める
どんなにお説教したり、強烈に叱ったりしても、子どもにとっては自分の存在を認めてくれない人の言うことを聞こうとはせず、本人のスキルとして身についていきません。一つひとつのやり取りの中でお子さんに対して“いいね”などとお子さんを認める声かけを重ねていくことも大事なポイントです。
そしてソーシャルスキルトレーニングを通して、お子さんの引き出しにいろいろなスキルを増やしていき、家庭や学校生活でも実践してもらいながら、将来的にうまく使いこなせるようになっていくことが目標となります。
変化し続けるこの社会の中で、相手の気持ちを理解しながら、適度に自己主張をすることや、他者と程よい良好な関係をつくることは、生き抜いていく力になると思います。
文責:坂牧円春
画像:いらすとや
参考文献:
・LD・ADHDへのソーシャルスキルトレーニング 小貫悟・名越斉子・三和彩
・あたまと心で考えよう SSTワークシート 社会的行動編 LD発達相談
ソーシャルスキルトレーニング
【ソーシャルスキルトレーニングのプログラム例】
1.インストラクション
2.モデリング
3.リハーサル
4.フィードバック
5.般化
【担当】臨床心理士・公認心理士
【料金】$160/h (時間外料金がかかることもあります)
初回は医師の診察が必要となります(状況によっては保険を使うことも可能です)。
実際にソーシャルスキルトレーニングをはじめる前には丁寧にアセスメントをおこない、お子さんがどんな場面で、なぜ困っているのかを理解することも重要です。その上で、見えてきた課題の中から優先順位を決めて、具体的なスキルの習得をサポートしていきます。
心配や気になること、困りごとなどお伺いしながら、保護者の方と、お子さんへの関わり方や工夫などを一緒に考えていくこともできます。お気軽にご連絡ください。ご希望や気になることがありましたら、お気軽に日本人会クリニック(TEL:6467-0070)にお問い合せください。