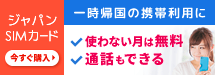クリニックからの手紙 「言葉の発達と「人真似」の重要性」(6月号 2024年)
01 Jun 2024
言葉の発達と「人真似」の重要性
言語聴覚士・公認心理士 鈴木利佳子
最近、書棚を整理していたら、非常に興味深い本を見つけました。10年ほど前に購入してそのまま書棚に眠っていた本でした。「<脳とソシアル>発達と脳—コミュニケーションスキルの獲得過程(岩田誠・河村満、2010医学書院)」です。非常に私の興味をそそる題名で、即買いしたものの、なぜか読まずに大切に保管されていた様子です。改めて読んでみたら中身がとても興味深く、一気に読んでしまいました。今回はその中から私が興味深いと感じた「コミュニケーションスキルの獲得と脳」の章から「ひとまねの重要性」をご紹介します。
言葉の獲得は脳機能の発達と関係が深いのですが、その中でも「ひとまねをする脳機能」が言葉の獲得とどのように関わっているか、ということについて記述されていました。
実は言語機能に関わる左脳の言語野は胎生9ヶ月までに形成されると言われています。胎生4ヶ月までには大脳の左右機能分化が確立し音の弁別が可能になると言われています。お腹の中にいる時点、それも妊娠4ヶ月目には言語脳の基礎が出来上がるというのは驚きですね。もちろん生まれた後に脳は刺激を受けながら大きく変化していきます。4ヶ月で見たり聞いたりする力と記憶する力が育ち、その中で言語機能が発達していきます。そしてその4ヶ月の間に対人関係、社会性の基礎が育つと言われています。生まれて半年くらいで喃語(なんご)が始まり、1年くらいで単語を話し、2年くらいで2語文を話すようになると言われています。この期間にたくさんの言葉に触れ、人との交流を楽しみ、人とやりとりする楽しみを知ることが言葉の発達に大切なこととなります。

言葉を話し出す前の乳幼児でも、じっとこちらの様子を見て、表情を真似したり、動作を真似したり、声を真似することがよくあります。幼児期の模倣能力は全般的な知的能力だけでなく、言語発達、さらには協調性や共感能力などの社会性を予測する因子となることが示されています。真似する能力「ひとまね」は、ヒトのコミュニケーション能力の発達過程にとって重要な基礎となっています。「人真似(ひとまね)」の能力は他者を自分に置き換えて認識する機能と関係しています。そして、コミュニケーションに大切な『相手の心の理解』を可能にしていると言われています。
真似には、「相手の顔の表情を真似る」、「手の動きを真似る」、「言葉や声を真似る」、「道具を用いた動作を真似る」があります。また、「道具を用いているフリ」の動作(例:包丁でものを切るフリの動作、手刀でトントン)、適切ではない道具を用いたみなし動作、(例:櫛を用いて歯磨きの真似をする)もあります。
言葉はコミュニケーションの道具です。自分の考えや思い、見たり聞いたりしたこと、知識などを他人に伝えるために使われます。「言葉という音声記号を用いて意思を伝達し合う」「言葉という文字記号を用いて意思を伝達し合う」「身振りサインという記号を用いて意思を伝達し合う」手段、道具です。
言葉の発達の遅れを主訴にクリニックにいらっしゃるお子さんを見ていると、「真似をする」がむずかしいお子さんが多くいらっしゃいます。
逆に言葉をまだ話していなくても、こちらをよく見て真似ようとするお子さんはその後「言葉」の伸びが期待できます。逆に言葉を発するお子さんでも、真似をすることが苦手なお子さんは言葉をコミュニケーションの手段として上手に使用することが難しい場合があります。例えば「おうむがえし」、これは、相手の言葉の音をそっくり真似ているのみでコミュニケーションの道具、手段としては上手に使用できていません。また、CMや店内放送のフレーズを丸ごとコピーして繰り返すこと。これも言葉を使っていてもコミュニケーションの道具としては使用できていません。

「真似をする」脳内機構はミラーニューロンシステムが関与しています。ミラーニューロンシステムは、他者の動作の認識に関わるだけではなく、その意図を理解する際にも働いていると言われています。このシステムに問題があると、他者の動作の認識や他者の意図を理解することが難しいと言われます。

多くの自閉症スペクトラム(ASD)例では模倣の障害があると言われており、そして言語発達が遅れることが多いと言われています。言語学習には模倣能力が不可欠であり、言葉の使用のためには相手の意図を理解し、どの場面でどんな言葉を使えば適切なのかという文脈の理解が必要です。ASDでは言語行動の背景を理解することが難しいことも言葉の発達を妨げる一因となっているようです。幼少期のASDの評価には「言葉の遅れ」が評価項目にいくつか含まれています。言葉を話し、会話ができるようになったお子さんでも、学童期の学習の遅れとして現れることの多い言葉の発達障害を持つお子さんの多くは、状況の理解や心情の理解が難しい場合が多くあります。これは、相手の意図を理解し、どの場面でどんな言葉を使えば適切なのかという文脈の理解が難しく、言語行動の背景を理解することが難しいことが関わっているのだと思います。そのため、適切な言葉を使用して自分の気持ちや思っていることを説明することも苦手な場合が多くあります。
もちろん言葉の遅れを持つ子が全てASDではありません。言葉の遅れにはいろいろな要因があります。しかし、「模倣をするか」という視点から言葉の発達を評価するという視点は非常に興味深い視点です。確かに、言葉の評価をする上で言葉を真似するか、どのように真似するか、というのはその後の言葉の訓練を左右する大きな視点になります。また、言葉の音を真似できなくても、動作を真似するか、どのように真似するかも重要な視点です。真似をするためには相手に視線を向けて相手を観察する必要があります。相手に注意を向けられるかな?じっと観察できているかな?全体を見ているかな?相手の意図を理解できているかな?その関わりを楽しんでいるかな?という視点もとても重要です。
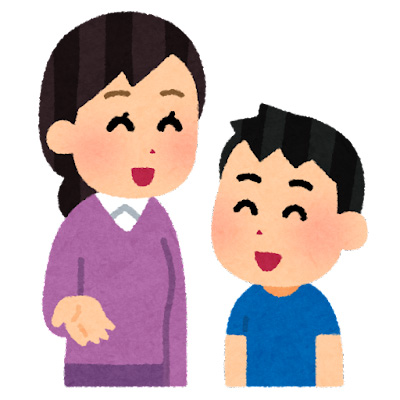
もし、身近なお子さんで「言葉が遅いな」と心配になる場合はどんな言葉を話すかと共に「動作を真似するかな」「道具の使い方を真似するかな」「言葉(言葉の音)を真似するかな」「表情を真似するかな」「真似するための関わりを楽しんでいるかな」という視点で見てみると、いろいろなことが見えてくると思います。
発達障害は脳機能の問題と言われています。発達障害と一言で言ってもいろいろなタイプがあり、それぞれ個々に様子が異なります。それぞれの子どもたちは定型発達とは異なる発達の様子を見せますが、驚くべき才能を持っていることも多くあります。個性豊かな子どもたちとの日々はたくさんの発見や驚きの連続です。それぞれ苦手なこともありますが、得意なこともあります。個々の子どもたちの発達に合わせ、私たち大人はどんな手助けができるかな、と日々思いながら私は子供達に向き合っています。
今回は「ひとまね」という行動を通じて言葉の発達を考える興味深い視点をご紹介しました。
文責・画像:鈴木利佳子
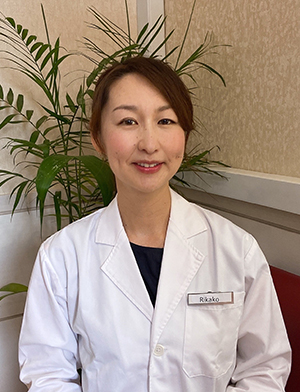
プロフィール:鈴木利佳子(すずき りかこ)
2003年言語聴覚士、2021年公認心理師国家資格取得。言語聴覚士として日本の病院で約18年間勤務、2021年来星。趣味はダイビング、腹話術、旅行、観劇、音楽鑑賞。
<専門資格>
* 日本言語聴覚士協会認定言語聴覚士(言語発達障害 領域、小児構音障害・吃音領域、失語・高次脳機能障害領域)
* 公認心理師
* 日本摂食嚥下機能障害学会 専門療法士、日本臨床栄養代謝学会
NST専門療法士
* 認知症ケア専門士