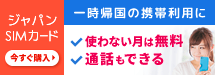言語発達に関する疑問:「たくさん話すのに、うまく伝わら ない」のはどうして? ―自分の経験を伝える「ナラティブ」の力を育む重要性―(2月号 2025年)
01 Feb 2025
言語聴覚士・公認心理士 鈴木利佳子
言葉には「伝達・コミュニケーション機能」と「思考・学習機能」という2つの重要な役割があります。幼児期や学童期にこれらの機能が発達することで、子どもは周囲と交流し、考える力を深めていきます。
乳幼児期には、発達段階ごとに言葉の発達をチェックします。「1歳半健診」では、「ママ」「ワンワン」など簡単な言葉を使えるかどうか、「伝える力」「わかる力」「人と関わる力」が育っているかを確認します。また「3歳児健診」では、3語文(例:「ママ かいしゃ いった」)を話せるか、自分の名前を言えるか、色・大きさの区別ができるかを確認します。
乳幼児健診で「言葉の発達は問題なし」と評価された子どもでも、幼稚園年長や小学生になると「よく話すけれど、内容がわからない」といった相談が親御さんから寄せられることがあります。お子さんに幼稚園や学校の出来事について質問すると、いっぱい話してくれるけど「いつ?」「どこで?」「誰が?」「何を?」「どうして?」と質問して細かい内容を聞き出したり、推測したりして、言いたい話の内容をやっと理解できることがあります。また質問しても「わかんない」と答えて会話が終わってしまうことがあります。小学生のお子さんでは、「学習」や「コミュニケーション」を心配されるお子さんに、このような様子が見られることがあります。日常会話は成り立ち、言葉の遅れはなさそうなのに、なぜなのでしょうか?
ナラティブとは?
家族や友達との日常会話では、話の背景や状況を共有しているため、細かい説明を省略しても会話が成立します。一方で、背景を知らない相手に物事を説明するには、「誰が」「いつ」「どこで」「何を」といった具体的な情報や、話の流れを順序立てて説明する力が求められます。このような経験の語りやお話の語りを「ナラティブ」と言います。ナラティブとは、時間的に連続した出来事を、順序付けてことばで表現する営みであり、学習言語の一つです。
ナラティブの力には「語彙力」「構文力」「推測力」「記憶力」「相手の心の状態を知る力」など様々な知的な能力が関わってきます。
5歳頃にはナラティブの基本的な力を獲得するといわれています。聞き手にわかるようお話するには、適切なことばを使い(語彙力)、正確な文を構築し(構文、助詞、語の変化)、話のすじに沿って文をつなげていく力(起承転結:主人公、事件、結果などの話の構成要素の認識)、因果関係を捉えた表現(推理力、知的能力)が求められるため、高次の言語能力や認知を必要とします。また、相手に理解してもらうように話を組み立てるには心の理論の発達(他者の心を推測し理解する能力)、ワーキングメモリーの発達も必要となります。
ナラティブの力
学習障害、というと「読み書きの障害」が有名ですが、読み書きの苦手な子どもたちの言語評価を行うと、言語発達の問題が根底にある子どもたちが多く、そしてナラティブの苦手さを持っている子どもたちが多くみられます。
学習障害(LD:Learning Disability)の定義にあるような「知的遅れはないが、聞く、話す、読む、書くの習得と使用に著しい困難を呈する」の中の「聞く・話す」の習得困難は、日常会話レベルの話ではありません。聞いた話の内容を理解する力、考えや意見を人に分かるように話す力です。つまり、学童期以降の言語の問題はコミュニケーション言語よりは、思考・学習のための「学習言語」の習得の問題と言えます。したがって、この学習言語の問題の有無は「言葉を喋るかどうか」だけでは判断できません。言語理解と言語表現の力を掘り下げてみることが必要です。しかし、ナラティブは従来の言語発達検査では評価できない部分と言われています。世界でも広く利用されている代表的な児童用知能検査WISC検査で「言語理解」の力が高いと評価されていてもナラティブの力が弱いことが多くあります。WISCでは多少文の組み立ての力が乏しくても点数が取れてしまうからです。
ナラティブはある出来事を語り手がどのように認識しているか、どのように意味づけしているかを反映します。例えばある男の子が「A君が僕のおもちゃをとった、だから叩いたんだ」と語った場合、「A君が僕のおもちゃをとった」「僕がA君を叩いた」という2つの出来事が結び付けられています。人を叩く行為は社会的に好ましくない行為ですが、「A君が僕のおもちゃを取った」という出来事と結びつけられることで、ある程度の正当性が認められ、意味づけられます。もしこの2つの出来事の語りが「僕がA君を叩いた。それでA君が僕のおもちゃを取った」では出来事の意味は全く異なるものとなります。私たちはナラティブの中で出来事を意味づけ、それを他者と共有します。もしこの語りが「A君が僕のおもちゃをとった、だから悔しくて叩いたんだ」「A君が僕のおもちゃを突然とった、だからびっくりして叩いたんだ」このように気持ちや状態を表す用語を上手に使って語られたとしたら、聞き手は状況がよくわかり、また話し手の気持ちもよくわかります。ナラティブはこのように、気持ちや状態を表す言葉を適切に使って表現し、聞いている人の感情も推測しながら語る力を持っていることで、より伝わりやすい「語り」となります。
ナラティブの力を育てる
ナラティブの発達を見ること、子供の「語り」に注目することで、言語発達の力、学習の力を推測できると言われています。英語圏では、学習言語の評価や指導に「ナラティブ」が活用されています。日本でも言語発達や学習支援の現場では「ナラティブの力」が注目されており、ナラティブの力を評価し、向上させる訓練方法の研究が進んでいます。また、心理学、社会学、それらに基づく様々な臨床領域、医療の領域でもナラティブが注目されています。ナラティブの力を向上させることは、学習や言葉の力を向上させることにつながります。
ぜひお子さんの語りに耳を傾け「ナラティブの力」に注目してみてください。
「ナラティブの力」は、言葉で自分の考えや経験を整理し、他者に伝える能力を育むための重要な要素です。この力が発達すると、学習や対人関係のスキルが向上し、子どもが自信を持ってコミュニケーションを取る基盤となります。日常生活の中でお子さんの「語り」に耳を傾け、共感しながら話を引き出すことで、ナラティブの力を育てていきましょう。
文責・画像:鈴木利佳子
参考文献:
田中裕美子 (2016) ナラティブを用いた言語評価 コミュニケーション障害学 P.33 ( 1 )、P.27 - 33
入山満恵子ナラティブを用いた言語指導法の開発に向けて ― 児童2名への実践を通して ―新潟大学教育学部研究紀要
第14巻 第2号
仲野真史 ナラティブの発達と支援特.殊教育学研究
P.47 P.183−192、2009